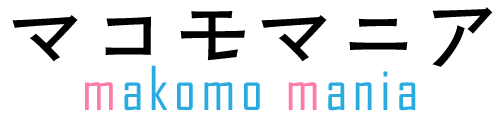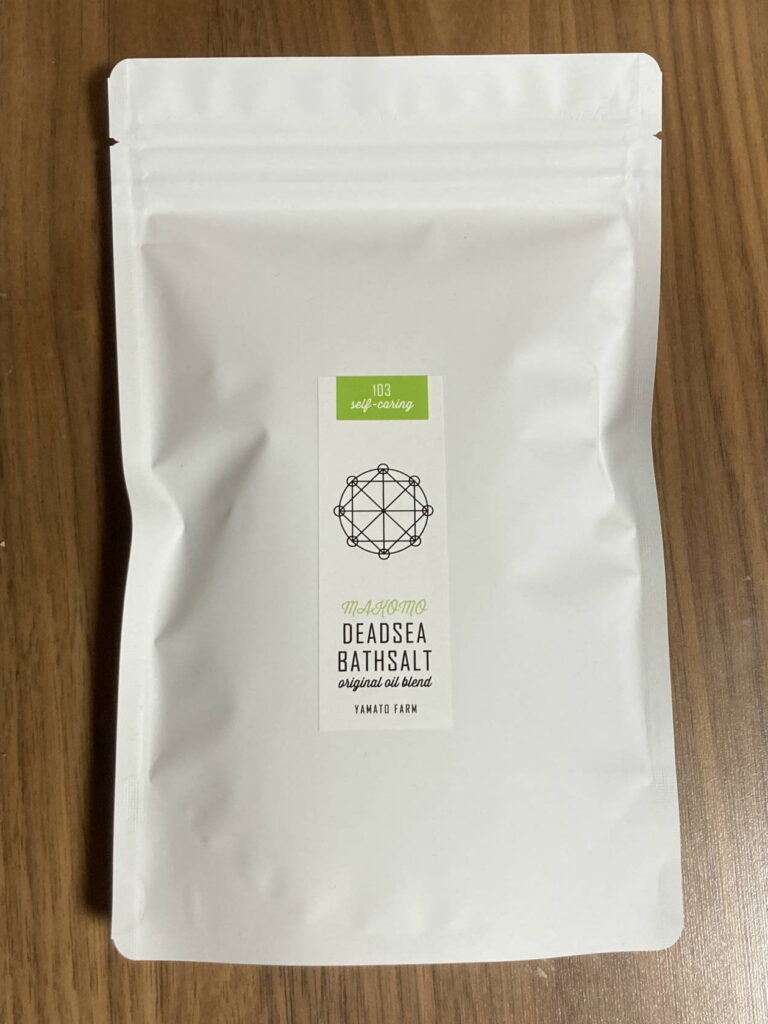【1】マウス神経膠腫細胞を対象に、マコモダケの有効成分Makototindoline を投与したところ、マウスス神経膠腫の細胞増殖を抑制したことから、マコモダケは神経細胞調節作用を持つと考えられています。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22672800【2】マコモダケには、破骨細胞抑制作用を持つ機能性成分が含まれていることから、マコモダケは骨の健康、更年期障害予防効果を持つことが期待されています。
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17090930【3】マコモダケは乳白色で柔らかく,タンパク質やビタミンB2を含む風味の良い野菜として中国料理で利用されています。豚肉や鶏肉とのいため物が美味しく、最近では日本でも特産品として栽培が始まっている。
マコモダケ(真菰筍)は、イネ科の多年草「マコモ」の茎が黒穂菌(Ustilago esculenta)の感染によって肥大化した部分で、食用として親しまれています。近年、マコモダケに関するさまざまな研究が進められています。
1. マコモダケの形成メカニズム
マコモダケの形成には、マコモと黒穂菌の共生関係が重要な役割を果たしています。静岡大学の研究では、黒穂菌が産生する新規の植物ホルモン様物質がマコモの茎の肥大化に関与している可能性が示唆されています。
2. 抗酸化機能の研究
東海大学の研究において、マコモダケ抽出物の抗酸化活性が評価されました。この研究では、マコモダケ抽出物が酸化防止剤としての機能を持つ可能性が示されています。
3. 栽培技術と貯蔵方法の検討
水田の転作作物としてのマコモダケの品種特性や貯蔵方法に関する研究も行われています。この研究では、マコモダケの栽培技術の向上や適切な貯蔵方法の確立が検討されています。
4. 地域での普及活動
青森県板柳町では、平成16年に中国からマコモダケを導入し、栽培技術の向上や産地化を目指した研究会が活動しています。このような地域での取り組みにより、マコモダケの普及と生産拡大が進められています。
これらの研究や活動を通じて、マコモダケの生産性向上や機能性の解明が進み、今後の利用拡大が期待されています。