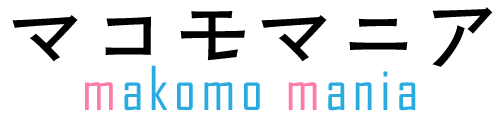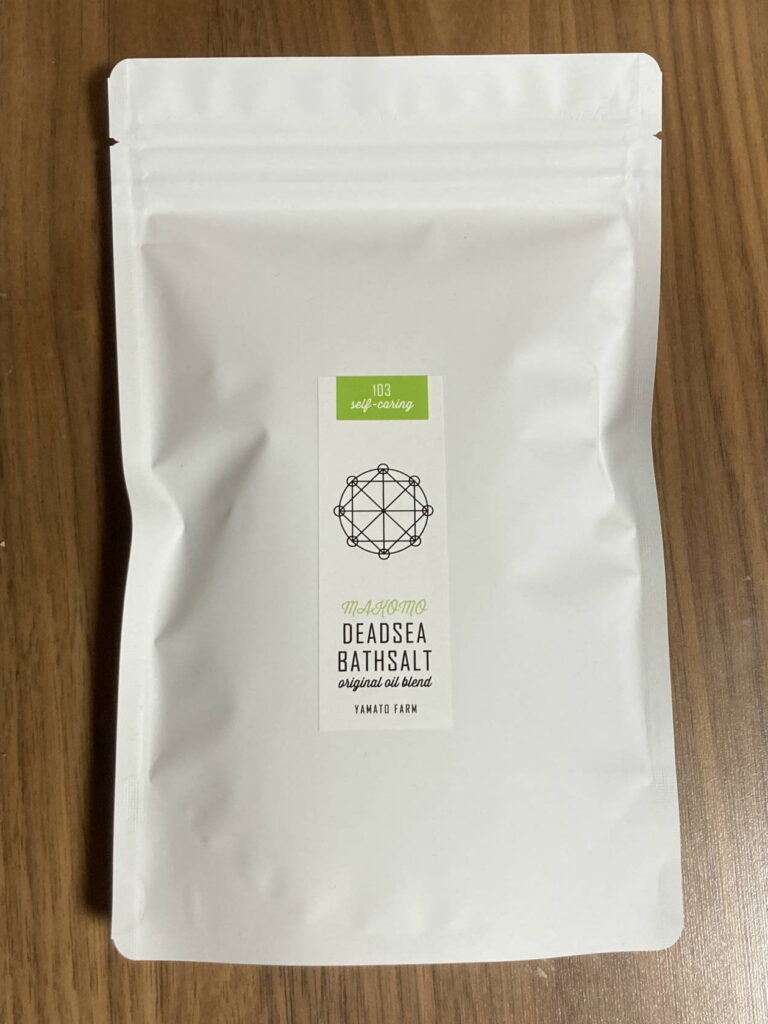菰枕(こもまくら)とは、菰(こも)=真菰(まこも)や藁(わら)などの草を編んで作られた枕のことです。日本では古代から使われ、特に健康・浄化・安眠のための寝具として重宝されてきました。
1. 古代~神話時代(~8世紀)
🌿 神事と菰の関係
- 真菰(まこも)は神聖な植物とされ、伊勢神宮・出雲大社などの神事に使われてきた。
- **「出雲の真菰」「伊勢の大麻」**と並び、厄除けや浄化の効果があると信じられた。
- 古事記・日本書紀にも、真菰が神聖な草として登場。
🌿 草枕の原型
- 寝具の歴史の初期段階では、柔らかい草を枕にしていたと考えられる。
- 当時は**「草枕(くさまくら)」**という言葉があり、旅先などで簡易的に使われた。
- 和歌にも「草枕」が登場し、旅人が野宿する様子が詠まれることが多かった。
2. 平安時代(794年~1185年)
🌿 貴族の寝具としての菰枕
- 平安貴族は、真菰を敷物や枕に使用していた。
- 風通しが良く、夏場の寝具として愛用された可能性がある。
- 「枕草子」には、当時の寝具や草を使った生活の様子が記述されている。
🌿 神事・仏教との関わり
- 寺院では、真菰を敷物や寝具として利用。
- 真菰には「邪気を払う力」があるとされ、仏教の修行僧が使用したとも考えられる。
3. 江戸時代(1603年~1868年)
🌿 庶民の間に広がる
- 農民や庶民が、菰(わらや真菰)を編んで枕を作り、寝具として使用。
- 「涼しく、蒸れない」という特徴から、夏の枕として重宝された。
- 江戸の町人文化が発達する中で、シンプルな菰枕が一般家庭にも広がる。
🌿 漢方・健康枕としての菰枕
- 漢方の影響で、「真菰は体を浄化する」という考え方が広まり、健康枕としても使われるようになる。
- 「菰枕で寝ると邪気が払われる」と信じられ、厄除けのために使用された。
4. 明治~昭和時代(1868年~1989年)
🌿 近代化と共に消える
- 明治時代以降、西洋文化の影響で、綿や羽毛を使った枕が主流に。
- 都市部では菰枕が減少し、田舎や伝統的な家庭でのみ使われるようになった。
- しかし、一部の農家や職人が手作りの菰枕を作り続ける文化は残る。
5. 現代(1990年~現在)
🌿 エコ・健康志向で再注目!
- ナチュラルライフやオーガニックブームの影響で、再び菰枕が注目される。
- 「通気性がよく、自然素材で快適」という理由で、特に夏用の枕として人気。
- 無農薬・手作りの菰枕が通販やオーガニックショップなどで販売されている。
- 「エネルギーを整える波動枕」としてスピリチュアル的な視点でも評価されることも。
6. まとめ
菰枕は、古代から日本人の生活や信仰と深く関わってきた寝具です。特に、健康・安眠・邪気払いのために使われ、現代でもエコでナチュラルな枕として再び人気が高まっています